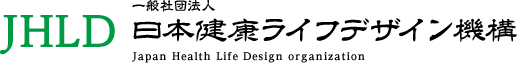メッセージ
医食同源とは、日頃から栄養バランスの取れた食事をとることで病気を予防し健康長寿を達成しようという考え方です。医食同源という言葉は中国の「薬食同源」に由来します。中国には古くから薬と食物はその源が一つであるという考え方がありました。現在でも漢方薬にその思想が受け継がれています。ところが現代日本では薬というと多くの場合は化学合成薬を指します。そこで薬を医療に置き換えたのが医食同源です。
身体によい食品を日常的に食べて健康を保てば、特に医療を必要としないという意味が医食同源に込められています。
むし歯不正咬合や歯周病、がん、糖尿病、脳卒中、心疾患など多くの疾患の根本原因は、美味しさを過度に追求した食事に求められます。また、十分な食品栄養学の知識はあっても、歯の疾患や口腔機能低下症のために噛んで食べることができない高齢者もいます。
我が国のような超高齢社会においては、歯科医療と栄養学が連携し、医学と歯科医学および食品栄養学を総合的に学修した人材を育成しなければ健康長寿社会の実現は困難です。さらに健康づくりには栄養のほかに運動と心の健康が必須ですから、運動学や心理学・精神医学の専門家の講義も重要です。
本機構では、このような課題を解決するために現代日本における屈指の講師陣にお願いして遠隔教育の教材作成を行っていただきました。この遠隔教育を受講した方の中から、医食同源を実践し、次世代の人々を教育する人材が多勢育つことを期待しております。